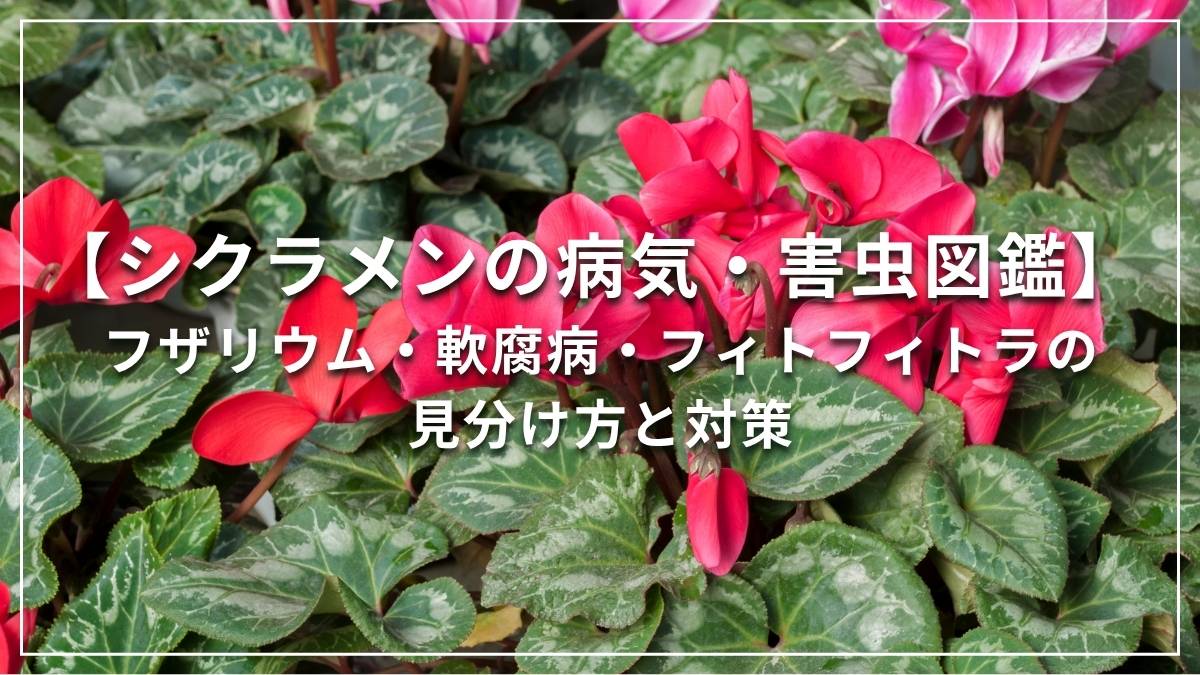シクラメンは美しい花を長く楽しめる人気の植物ですが、病気や害虫の被害を受けやすい一面もあります。特に「灰色カビ病(ボトリチス)」「軟腐病」「萎凋病(フザリウム)」「疫病(フィトフトラ)」などは注意が必要です。この記事では、それぞれの病気や害虫の症状や予防法、対処法について詳しく解説します。
シクラメンの病気・害虫を防ぐために
株や根に傷がつくと、そこから病原菌が侵入しやすくなります。植えつけの際にはなるべく根を触らないようにして、優しく植えつけるようにしましょう。
植えつけは、無菌の新しい培養土を使用し、殺菌剤を散布しておくと安心です。
植え替えや花がら摘みなどお手入れをする際には、感染予防のために、必ず手洗いと道具の消毒をするようにしましょう。
締め切った場所や過湿状態は病気の原因になります。植物と植物の間にある程度スペースを空けて風通しよい場所で、過湿に気を付けて育てましょう。水やりは花や葉・球根部にかからないようにして株元にあげましょう。
例えば10℃を超えるような気温の変化は、シクラメンにとってストレスになります。購入直後の直射日光や、日なたから半日陰に移動する際、室内でも夜間に冷え込む窓辺などは注意するようにしましょう。
シクラメンのよくある病気と対策
灰色カビ病(ボトリチス)
シクラメン以外にも発生しやすい病原菌です。葉や花が萎れる症状を見て、軟腐病と間違えてしまうことがありますが、綿毛状のカビが生えるかどうかで違いが分かります。
| 症状 | ✔茎が枯れて、花や葉が鉢の縁に垂れ下がる ✔花弁に茶褐色の斑点が現れ、やがて腐敗 ✔塊茎に灰色の綿毛状カビが発生  塊茎は灰色の綿毛状のカビで覆われ、幼葉や花芽に伝染します。葉が密集すればするほど発生しやすくなります。  花弁には、斑点状のものが浮かび上がることがあります。(白色や濃い色の品種は、斑点はほとんど目に見えません。)  感染が進行すると、花弁の班は茶褐色になり腐敗していきます。 |
| 病原菌 | ボトリチス(糸状菌) |
| 感染経路 | 胞子は、水と空気の流れによって運ばれる他、昆虫のはたらきで拡がります。傷口だけでなく、萎れた葉や花などから侵入することもあります。 |
| 予防方法 | ✔湿度95%の状態が3~4時間続くと、胞子が発生しやすくなります。風通しよい場所で、過湿に気を付けて育てましょう。 ✔窒素肥料のあげすぎに注意しましょう。チッ素(N)濃度が高すぎると柔らかく、感染しやすい芽が育ってしまします。 ✔月に一回のスイッチ顆粒水和剤(スイッチ有効成分: フルジキソニル 25% +シプロジニル 37.5%)の散布が有効です。灰色カビ病(ボトリチス)の他にも炭疽病にも効果があります。 |
| 対処法 | ✔感染部位はすぐに取り除き、殺菌剤を散布しましょう。 ✔株の上から水をあげると、胞子が飛び散る可能性があります。株の根元に水をあげるようにしましょう。 |
上記の情報は海外での試験結果をもとに作成しております。日本で許可・使用については、最新の状況を御確認の上、自己責任で確認をお願いします。
軟腐病
匂いを放つ点が、軟腐病の大きな特徴になります。疫病(フィトフィトラ)や萎凋病(フザリウム)は、軟腐病と違い、塊茎は固いままになります。
| 症状 | ✔塊茎が柔らかく腐り、悪臭を放つ ✔葉や茎が溶けるようにしおれる ✔1~2日で進行する  塊茎が柔らかくなり、指で押さえただけで潰れるほどになります。球根の内部が腐敗し、腐って悪臭を放ちます。 |
| 病原菌 | エルビニア属の細菌 |
| 感染経路 | 植え替えなどでできた傷口から侵入します。植え替え作業の数日後に発症することが多く、植え替えなどでできた傷口から侵入します。細菌は土壌や水、植物の中で生存し続けます。 |
| 予防方法 | ✔高温(25~30℃)で多湿な環境で繁殖しやすくなります。風通しよい場所で、過湿に気を付けて育てましょう。 ✔温度を下げるための葉水は控えましょう。 ✔植えつけ時に球根を深植えしないようにしましょう。 ✔肥料は窒素過多に注意しましょう。 ✔ストレプトマイシン・有機銅水和剤などの農薬を予め散布しましょう。 |
| 対処法 | ✔感染した株はビニール袋に入れて廃棄しましょう。薬剤散布で病気を治すことはできず、防除方法としては、予防しかありません。 ✔病気の株を見つけてから一週間は、毎日他の植物が発病していないか確認するようにしましょう。 |
上記の情報は海外での試験結果をもとに作成しております。日本で許可・使用については、最新の状況を御確認の上、自己責任で確認をお願いします。
萎凋病(フザリウム)
| 症状 | ✔葉が黄~オレンジに変色し、一部がしおれる ✔葉柄の根元に紫~ピンクの胞子が出ることも ✔球根を切ると、導管に茶~オレンジ色の斑点  感染すると、葉の一部が黄色~オレンジ色に変わり、葉脈に沿って変色が拡がり、後に株の一部が萎れていきます。葉色の黄化は萎凋病以外の原因でも起こるので、判断には注意が必要です。葉柄の付け根付近に、フザリウムの胞子である紫-ピンクの斑点がみられることもあります。 |
| 診断法 |  病原菌は、酸性土壌で発病しやすいとされるフザリウム(糸状菌)になります。球根を水平に切ると導管にオレンジ~茶色の斑点がみられます。斑点は、球根の片側に集中する傾向がみられます。 |
| 病原菌 | フザリウム属(糸状菌) |
| 予防法 | ✔植えつけ時にできる傷口から感染するケースが多いようです。植えつけ時には株をなるべく触らないようにして優しく植えつけましょう。 ✔消毒済の無菌の土で育てるようにしましょう。 ✔28℃の高温多湿環境でもっとも発生しやすくなります。風通しよい場所で、過湿に気を付けて育てましょう。 ✔肥料は窒素過多に注意しましょう。 |
| 対処法 | ✔発病した葉は取り除いても株が回復することはありません。発病株はビニール袋に入れて廃棄しましょう。 ✔感染した土壌は必ず消毒を行いましょう。 ✔株の上から水をあげると、水の跳ね返りで病気が拡がってしまいます。水は株の上からかけず、根元にあげるようにしましょう。 |
疫病(フィトフィトラ)
フィトフィトラと呼ばれるカビは、根や茎を腐敗させ、多様な症状を伴います。フィトフトラの感染症状はフザリウムとよく間違われます。球根を切断し、導管が変色しているか維管束が変色しているかで判断可能です。
| 症状 | ✔感染した部位は、黒色や茶色に変色します。 ✔葉では、葉脈に沿って黒色や茶色の筋が広がります。 ✔球根を切ると、維管束が茶~黒に変色 |
| 診断方法 |  球根を水平に切った後さらに垂直に切断すると維管束が黒っぽく変色しているのが確認できます。斑点は、球根の全体に均等にみられる傾向があります。 |
| 病原菌 | フィトフィトラ(糸状菌) |
| 感染経路 | 根から感染して、根腐れを起こします。 |
| 予防法 | ✔水のあげ過ぎに注意し、土が完全に乾いてから水をあげるようにしましょう。 ✔フィトフトラ菌は、20~25°Cで最も繁殖しやすく、また13~15°Cの環境でも繁殖します。 |
| 対処法 | ✔発病株はビニール袋に入れて廃棄しましょう。 ✔感染した鉢をそのまま放置した後水やりをすると、胞子が散って、他の植物に感染する可能性があります。感染の可能性がある鉢はすぐに清掃し、片付けるようにしましょう。 |
炭疽病
| 症状 | ✔花首が細くなり黒く変色 ✔花芽や葉芽は小さいままで、葉が落ちる ✔黒く変色した部分に褐色の斑点を生じる  |
| 病原菌 | 炭疽病菌(Colletotrichum) になります。 |
| 予防方法 | ✔高温(23~28℃)で多湿な環境で繁殖しやすくなります。風通しよい場所で、過湿に気を付けて育てましょう。 ✔スイッチ顆粒水和剤(スイッチ有効成分: フルジキソニル 25% +シプロジニル 37.5%)の散布が有効です。4~5週間程度効果が持続するので、月に一回散布するようにしましょう。スイッチ顆粒水和剤は、灰色カビ病にも効果があります。 ✔炭疽病菌(Colletotrichum) は、ラナンキュラス、イチゴ、ニシキギ、ベゴニア、クチナシなどに宿主します。シクラメンと一緒に栽培するのを避けましょう。 |
| 対処法 | ✔株の上から水をあげると、病気が拡がってしまいます。 ✔発病した葉は取り除いても株が回復することはありません。発病株はビニール袋に入れて廃棄しましょう。 |
上記の情報は海外での試験結果をもとに作成しております。日本で許可・使用については、最新の状況を御確認の上、自己責任で確認をお願いします。
シクラメンの害虫
スリップス
スリップスとホコリダニは見分けることが難しいのですが、ホコリダニは若葉を攻撃するのに対して、スリップスは若葉と生長した葉が同時に攻撃されます。
| 症状 | 大抵の場合、被害が現れたときには既に遅く、花や葉に症状がみられます。 表皮下の組織内に卵を産み付けるので、刺された部分は褐色に変色し、壊死します。  被害にあった葉の全体が柏の葉のような形に変形します。 |
| 害虫 | スリップスがシクラメンに危害を及ぼすのは、幼虫期と成虫期になります。20~25℃の環境下でよく発育します。 |
| 予防方法 | ✔風通しよい場所で、ある程度スペースを確保して育てましょう。 ✔雑草などの除草をし、ウィルスに感染したと思われる株は除去しましょう。 |
| 対処法 | ✔薬剤防除をしましょう。 ✔発病した葉は取り除いても株が回復することはありません。発病株はビニール袋に入れて廃棄しましょう。 |
ホコリダニ
スリップスとホコリダニは見分けることが難しいのですが、ホコリダニは若葉を攻撃するのに対して、スリップスは若葉と生長した葉が同時に攻撃されます。
| 症状 | 花や葉に症状がみられます。 若い花や花芽に歪みが生じます。  若い葉のみ表面がデコボコし、光沢を帯びます。 |
| 害虫 | ホコリダニは自力で株から株へと移動することはできません。移動範囲は極めて狭く、1つの株に留まっていることがほとんどです。 しかしながら、作業道具などを媒介する他、コナジラミやスリップス・アブラムシなどの他の虫の脚や触角に付着して移動することがあります。 |
| 予防方法 | ✔お手入れの際には、手洗いと道具の消毒をするようにしましょう。 ✔早期発見のため、株の中心部分などを定期的にチェックするようにしましょう。 |
| 対処法 | ✔薬剤防除をしましょう。 ✔発病した葉は取り除いても株が回復することはありません。発病株はビニール袋に入れて廃棄しましょう。 |
シクラメンの生理障害
高温障害
シクラメンが良く育つ適性温度は、10~20℃になります。急激な高温(例えば30℃近い夏日)状態では、高温障害が発生します。
栄養が行き届かなくなった株は、生長が止まり花芽形成も遅れます。さらに耐性も崩れ、病気にかかりやすくなります。

解決策としては、夏日は風通しのよい涼しい場所で育てることが何よりです。さらに葉水をすることで、シクラメンの葉の表面温度を下げるのも効果があると言われています。
注意事項
本記事の内容は海外の試験結果に基づいて作成されています。日本での薬剤使用等については、最新の情報を必ずご確認の上、自己責任で対応をお願いします。
まとめ
シクラメンは、秋から冬を華やかに美しく彩るお花としてとても人気があります。病気や害虫対策・高温障害も、日ごろのお手入れや環境づくりに気をつけることで、十分に予防することができます。
大切なのは、風通しと清潔さを保つこと、株を傷つけないこと、急激な環境変化に気をつけること。そして異変に気づいたら、早めに対処することが健康な株を守るポイントです。ちょっとした気配りで、シクラメンは冬の間も美しい花を咲かせ続けてくれます。ぜひ今回ご紹介した対策を活かして、元気なシクラメンとの暮らしをお楽しみください。